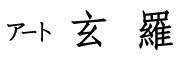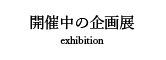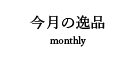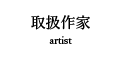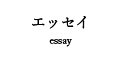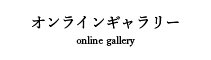蓮という花ゆえに
美しいがゆえに、何らかの象徴性を帯びてしまう花がある。薔薇は花の中でも、その王者である。「君は薔薇のように美しい」という女性に対しての賛辞は、おそらく誰も拒まないであろうが、今や本当に言葉に出して言うのは、歌の歌詞ぐらいかもしれない。だが、やがて枯れ果てて失われる花の美しさは、植物に限らず生命が持つ美というものが含む刹那的なものをどこかに含んだものだろう。
日本人にとって、というより仏教にとっての美しい花は蓮ということになるのに違いない。ブッダが誕生したとき、唱えた「天上天下唯我独尊」。その場所は、泥沼からすっと天空へ伸びた蓮の花の上だという。仏教の象徴的な花は、仏の座す蓮華座となり、仏を供養する散華では蓮の花びらをかたどった紙が舞い散る。蓮には、宗教性を表す特別な花というイメージが固定している。
蓮の意匠はさまざまだ。古代寺院の瓦にもあるし、仏を荘厳する空間では、花を展開した多くの文様が見られる。その象徴性があるがために、人々の思いが託されるのだろう。
わたしには、好きな蓮の写真がある。祈りの空間を主テーマにする写真家六田知弘氏がスリランカの石窟寺院で撮影した赤い蓮の作品だ。写真家が寺院の古びた木の拝礼台にふと目をやると、仏に手向けられていたという。艶やかだが、品のある美しさ。大阪市立東洋陶磁美術館が2014年に開催した「清らかな東アジアのやきもの×写真家六田知弘の眼 蓮」展の会場で、目の前にして立ちすくんだ。一枚を分けていただいた。一瞬、こころを惑わされそうになるが、妙なる姿に息をのみ、祈りの果てへと目をやる。命のまばゆさとはかなさを思う。
朝鮮王朝時代のものだろう。小さな銅製の蓮型香炉が、縁あって手元にある。高貴、清廉を求めた文人趣向を感じる。朝には、炉内に立てた一本の線香から一筋の煙が昇っていく。この美しい十六弁の蓮華の組み合わせがつくる絶妙な姿の向こうに、仏の宇宙があることを願って火を付ける。若くして亡くなった妻に向けて。
夏は蓮の花が咲き、お盆には死者があの世から戻るという。愛する者を喪った悲しみから、美の造形は生まれるのだろう。人は、蓮という花を通して、見えない世界へと行ってしまった者への追憶と祈りを重ねている。
黒谷誠仁(くろたに・まさひと) 玄羅(げんら)